内閣府のムーンショット計画の目標1『2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現』は、サイバネティック・アバターの開発やブレインマシンインターフェースなどの最先端技術を軸に、物理的・生物的な限界を超えて人々が自由に社会参加できる未来を描いています。
身体や脳の制約解放に最も貢献すると考えられる技術は、現時点のムーンショット計画の研究動向から見ると、サイバネティック・アバター技術と、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の組み合わせが最も中核的です。
• サイバネティック・アバター技術
遠隔操作可能なアバター(ロボットや仮想体)を使い、物理的な身体を超えて多様な活動に参加できる社会を目指していて、これにより身体的な制約(移動困難、障害、加齢など)を超えて仕事・教育・医療などに参画できるようになります
• ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)
脳波や神経信号を用いて、アバターや機械を「思い通りに」操作する技術で、BMIによって、身体が動かなくても意図を直接機械に伝えられるため、脳の機能を拡張し、さらなる自由度を実現でき、既に動物実験レベルでは脳信号から次の動作を予測する技術も進展していて、人間への応用も現実味を帯びています
• サイボーグ技術
義手・義足・パワードスーツなど、身体機能を直接拡張・補完する技術も重要で、特に侵襲型(体内埋込型)や、非侵襲型(装着型)のサイボーグ技術は、身体機能の大幅な補強や代替が可能になります
これらの技術は相互に連携し、アバターの遠隔操作やBMIによる意図伝達、サイボーグ技術による身体機能の拡張が組み合わさることで、身体・脳の制約からの解放を最も強力に推進すると考えられます。
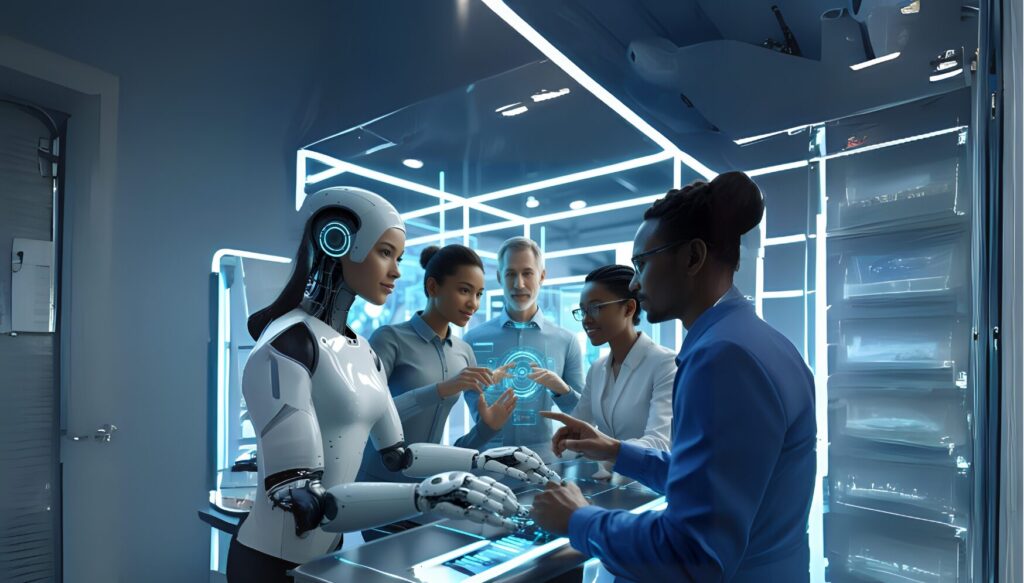
2050年の未来社会構想から考える「自身の役割」と「準備すべきこと」
1.未来社会で求められる役割
• 多様な社会活動への積極的な参加
地理的・身体的制約にとらわれず、アバターやリモート技術を活用して、さまざまな分野やコミュニティに貢献する
• 人とAI・ロボットの協働推進者
AIやロボットと共に働き、共創する場面が増えるため、テクノロジーとの協働をリードできる存在が求められます
• 新しい価値観・倫理観の発信者
技術の進展とともに社会規範や倫理観も変化するので、多様性や包摂性、テクノロジーとの共生について自ら考え、発信する役割も重要です
2.準備すべきこと
◇ テクノロジーリテラシーの強化
• サイバネティック・アバターやAI、量子コンピュータなどの基礎知識を身につける
• 新しいデジタルツールやサービスに積極的に触れる
◇ 柔軟な学びと自己変革
• 終身学習(リカレント教育)を意識し、変化する社会や技術に適応できる力を養う
• 異分野・異文化との交流を通じて、多角的な視点を持つ
◇ コミュニケーション力・協働力の向上
• 遠隔・バーチャル環境でのコミュニケーションやチームワークに慣れる
• AIやロボットとの協働経験を積む
◇倫理観・社会的責任の理解
• テクノロジー活用と社会的インパクトについて考え、自分なりの倫理観を持つ
• データリテラシーやプライバシー意識も重要
3.未来社会での「自分らしさ」の発揮
• 好奇心や探究心を持ち、自分の興味・強みを活かせる分野を見つける
• テクノロジーを「使う側」から「創る側」へと意識を広げる
• 社会課題の解決や新しい価値創出に主体的に関わる姿勢を持つ

アバター技術の発展に伴う倫理的課題に対しては、新たな法的枠組みの整備が不可欠であるという指摘は、複数の専門的議論により強く支持されています。
現行法は、アバターやサイバネティック・アバターを想定しておらず、プライバシー権や人格権、なりすまし、アイデンティティの保護、責任の所在など、多くの論点で十分な対応ができていません。
たとえば、アバターのなりすましや、本人の意に反してアバターが利用された場合の人格権侵害、プライバシー侵害などは、現行法の枠組みでは十分に保護されないケースが想定されます。
また、アバターを通じた活動が社会生活に現実の被害をもたらす場合、現実世界の法や倫理規範がそのまま適用できない場面が増えることも指摘されています。
このため、「アバター法」などの新たな法分野の必要性が提唱されていて、仮想空間やアバター社会に特化した法的枠組みを構築し、課題に対応することが求められています。
• アバターの人格権・プライバシー権の明確化と保障
• なりすましや偽装行為への迅速な法的対応
• アバターを介した行為の責任の所在や範囲の明確化
• プラットフォーム運営者の法的責任や義務の整備
• 国際的な枠組みとの調整(国境を越える活動が前提となるため)
技術の進展に合わせて、現実と仮想空間のギャップを埋める新たな法的枠組みの整備は、アバター社会の健全な発展と利用者保護のために不可欠です。
内閣府の公式ウェブサイトや科学技術振興機構(JST)、NEDOなどの関連機関のページで、ムーンショット計画の進捗や公募情報、イベント案内などが随時更新されています。



