「第6次エネルギー基本計画」とは、2021年10月に経済産業省より発表された、エネルギー政策の基本的な方向性を示すもので、新たな電源構成の目標(再生可能エネルギーの割合増加、火力発電の割合減少、水素・アンモニア発電の導入など)が設定されています。
省エネ設備投資や、FIP制度(売電収入に加えて補助金が上乗せされる仕組み)の導入など、エネルギーミックス実現に向けた具体的な政策も経済産業省が中心となって推進しています。
主要な目標
1.再生可能エネルギーの大幅な増加と主力電源化
2.火力発電への依存度低減
3.原子力発電の一定割合の維持
4.エネルギー自給率の向上
5.経済性の改善と国民負担の軽減
6.温室効果ガス排出量の削減
安全性(Safety)を前提とし、エネルギーの安定供給(Energy Security)、環境への適合(Environment)、経済効率性(Economic Efficiency)という「S+3E」の考え方に基づいていて、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた重要な中間目標として位置づけられています。
■電源構成の目標
1.再生可能エネルギー:36〜38%(2019年の18%から増加)
• 太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなどを含む
2.原子力発電:20〜22%(2019年の6%から増加)
3.火力発電:41%(2019年の76%から大幅に減少)
• 石油:2%
• 石炭:19%
• LNG(液化天然ガス):20%
4.水素・アンモニア:1%(新たに導入される電源)
■実現に向けた取り組み
1.再生可能エネルギーの導入促進
• FIT制度(固定価格買取制度)や、FIP制度の活用
• コスト低減と市場統合の推進
2.エネルギー効率の向上
• 産業・業務部門のエネルギー消費効率改善
• 高効率機器の普及促進
3.新技術の開発と導入
• 水素・アンモニア発電の推進(2030年度に電源構成の1%を目標)
4.電力システムの柔軟性向上
蓄電技術の開発や送電網の整備(再生可能エネルギーの安定供給のため)
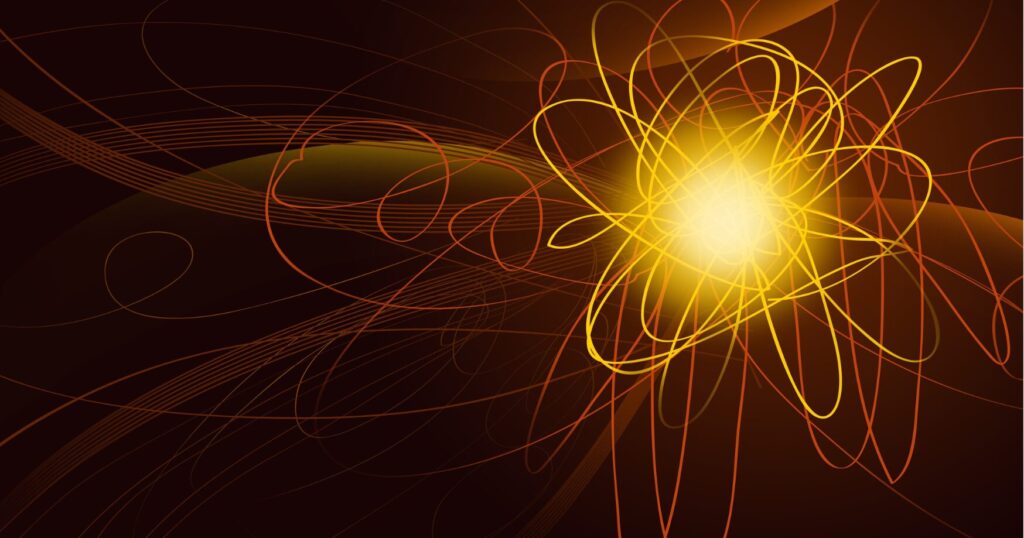
日本のエネルギー需給構造には、さまざまな課題があり解決策が検討されています
■主な課題
• 低いエネルギー自給率
日本のエネルギー自給率は11.8%と、OECD加盟国の中で下から2番目の水準にあり、これは日本がエネルギー資源の約9割を海外からの輸入に依存していることを意味し、エネルギー供給の安定性に大きな課題となっています。
• 化石燃料への高い依存度
化石燃料への依存は、地球温暖化や脱炭素化の観点から問題となっていて、中東からの輸入に頼る構造は、国際情勢の変化によるリスクを高めています。
• 再生可能エネルギー拡大への障壁
再生可能エネルギーの主力電源化に向けては、高い発電コストや系統制約などの課題が存在します。
■解決策
1.エネルギー自給率の向上
• 再生可能エネルギーの拡大:太陽光、風力などの再生可能エネルギーの導入を促進し、経済的に自立し脱炭素化した主力電源化を目指します。
• 原子力発電の位置づけ:安全性を最優先としつつ、脱炭素化の選択肢として原子力発電の活用を検討します。
2.エネルギー源の多様化
• 水素・蓄電・分散型エネルギーの推進:技術開発に着手し、エネルギー供給の多様化を図ります。
• カーボンリサイクル:CO2由来の原燃料製造など、国内資源を活用する技術の導入を進めます。
3.省エネルギーの徹底
• 省エネ法の強化:省エネ法と支援策を一体的に実施し、徹底的な省エネを継続します。
• シェアリングエコノミーの促進:自動車のシェアリングなどを通じて、必要なエネルギー量の削減を図ります。
4.循環経済(CE)の推進
• 資源の循環的活用:鉄スクラップや廃プラスチックなどの廃棄物資源の再利用を促進します。
• 二次流通の促進:ストック製品の有効活用を通じて、新規資源の消費を抑制します。
カーボンニュートラルと循環経済の融合により、2050年にはエネルギー自給率を64%まで向上させる可能性が示されています。
エネルギー需給構造の課題解決には、技術革新、制度改革、国民の意識改革など、多面的なアプローチが必要となります。



